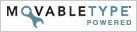« 門を開く |
メイン
| 操縦術 »
声を聴いた
認めることの何が悪いのだろうか。
認めることをどうして畏れるのだろうか。
それが何も生まないから。
結局は、ぱっと弾け散るように生じて、そのまま空気の中に薄れて消えていくだけの将来しかもたないから。
それをナゼ畏れるのか。
そんなものに捕らえられるのが怖い。
ナゼと問うたところで知ることはできない。ナゼと問われるべき理由がそもそも存在しない。それならばナゼとは問うまい、けれど、あの厭な感覚。蛇のウロコを逆さから撫でてしまった時のような鳥肌立つ感覚。生理的に拒否を出す感覚。二度も三度も。
Read More... あり得ないものよりも今そこにあるものを選択する、そのような現実的な生き方が羨ましい。必要のない苦悩から生じる精神の破綻と、言い切ってしまう強さが羨ましい。絶望するなかれ、というのが根底にある真理なのだと、最後に付け足す優しさの部分が嫌いだ。
針のようになるのならば、棘のように刺さるのならば、いっそナイフになっていただきたい。それで失神しそうなほどに切り裂いていってくれたほうがいい。血のでない痛みというのは手に余って厭だ。切り開かれた瞬間に治癒に向かうことがわかるような、はっきりとした傷のほうが良い。
どうせならナイフになっていただきたかった。
こんな、中途半端な棘なんかではなくて。
アラタさん、
たとえ私が需要と供給の関係でだけ視線かちえたモノであっても。
あのときに与えられた諸々は、未練つかないようにきっぱりと捨ててしまいました。意識して忘れようとしたわけでもなく、単に思い出す必要もなかったので薄れかけていた諸々は、水のそこから浮かび上がるようにして目覚めては私の寝入りばなを襲撃するし、その全てがまた無駄なやり直し繰り返しであると思います。
なぜこれしきのことにこれほど悩まされるのかと思いもするし、それ以前にもっと根本的な部分で大切なことを忘れているような気にもなるのです。
けども。
けれども。
厭なのです。ひたすらに厭です。純粋に厭です。
2月だって二度も三度も貴方は歩いて来るしそうして謝るし、くだらないことと自嘲して諦めかけたところに降って湧いたように生じたあの二秒に到るまで、やっぱり私は今回と同じ自己否定しか貴方からもらっていなかった。
そう。あの時の自己否定は、私が背中から受けた傷から入り込んだのではなかった。あの人という外的要因に誘導されるようにして、私の内に自ずから生じたものだった。それが何だか背中の傷の痛みとごったになって、原因は何なのかどこなのかわからなくなっていたけれども。
二度も三度も歩いたりしないで、自分のいるところに収まっていてくれればいいんです。確保された立ち位置が与えられているのだから。
風も受けない、まるで幽霊のように私と重なって、音も立てずに剥がれていって、そういう静寂のなかにある気持ちにしか残らない余韻。嗅覚にも視覚にも触覚にも残らない、心の感情の中にしか残らない余韻。外部のどこにも頼りがいがなくて、本当にあったのかどうかも覚束無い。自分が勝手にみていた幻覚ではないかとすら思うような覚束無さ。自己否定に繋がるあやふやさ。
そういうもののなかで、鼓膜のそこに残る声だけがかろうじて繋がっている蜘蛛の糸のように、ウツツと狂気をつなぐのだけれど。
それすらもいっそ切れてくれたらばまだどちらかに転がれる救いようがあると思う時のある。
そんなような残酷な声でした。やわらかで。
Close...2005.07.30.23:58
| トラックバック (0)
|
▽トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://vega.sakura.ne.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/215